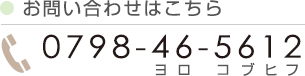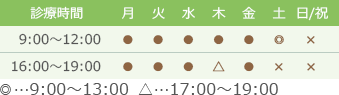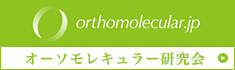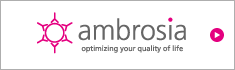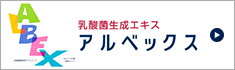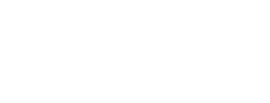IgA
こんにちは、院長の栗木安弘です。
免疫力をアップさせるためには、免疫グロブリンであるIgAが重要であることをTVで紹介されていました。加えて、「IgAを増やすには食物繊維やヨーグルトに摂取が有効」
とお偉い先生がおっしゃっていました。
しかし、IgA産生にはグルタミンとビタミンAというのは栄養療法では当たり前のことです。IgAに限らず、病気や健康に関しては、体の仕組みや生化学をきちんと理解した上でのコメントが必要ですが、多くは論文ばかりの研究結果を鵜呑みした専門家コメントが多いなぁと感じます。
全身を診る皮膚科
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科というのは皮膚だけしか見れないと思われ、大学病院の時も重症の皮膚疾患や術後の全身管理は内科や外科にサポートしてもらうことが度々ありました。そういった経緯から私自身は医者なのに皮膚しか診れない皮膚科に劣等感を感じていました。
局所対応は良い意味としては専門性が高いと言えますが、最近は美容ばかりで益々「木を見て森を見ない」対応が目立ちます。
皮膚というのは内臓の異常を敏感に反映します。
そのため皮膚トラブルには体の内側の対応が同時に必要かと思います。
内臓は内科の役割とお思いですが、その多くは決められた薬物治療ばかりです。
栄養療法では内臓疾患と栄養との関わりを随分教えてもらいました。
内臓疾患はたくさんあり、皮膚とも関連性はありますが、少なくとも、貧血、肝臓、消化管の病態把握と対応が皮膚科医には必要かと思っています。
ニキビと栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
ニキビの治療をしていても良くならない方は大勢います。
こうしたケースは外用剤の使い方やスキンケア指導がなされます。
確かにそれも大事でしょうが、栄養療法では病気の成り立ちというものを教わりました。
つまり、ニキビの成り立ちを考えた対応が必要となります。
教科書的にはニキビは、
①皮脂過剰、②毛穴のつまり、③ニキビ菌増殖による炎症が原因とされていますが、
こうした機序を生化学的に理解されていない皮膚科医は多いと思います。
生化学的な異常を評価するためには血液検査を行います。
ニキビに対して血液検査をする皮膚科は皆無ですが、皮膚も内臓のあらわれです。
食生活や栄養など、内側から体をよくすることがニキビの根本的な対策です。
栄養の勉強会
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先日は定期的に行われている勉強会でした。
参加者は歯科衛生士さんが多く、私はいつも栄養の講師をさせていただいておりますが、歯のことや歯科業界についても大いに学ばせてもらっています。
栄養療法を続けていると、皮膚科以外の医師や従事者と知り合いになることが多く、内科、整形外科、心療内科、歯科など違った知識を得ることができ、普段の診療にも大いに役立ちます。
医療は閉鎖的な世界です。皮膚や皮膚科診療での疑問や悩みについては皮膚科の世界で解決するものと思っていました。しかし視野を広げて、皮膚を体(栄養)の一部としてみることで意外と解決していくことが栄養療法を通じていつも感じています。
皮膚は教えてくれる
こんにちは、院長の栗木安弘です。
最近は皮疹を詳しく観察せず、電子カルテや検査結果ばかりを見ている皮膚科医も少なくありません。私が研修医だった頃、ひたすらカルテ記載ばかりを行って全く患者さんと目を合わさない先輩皮膚科医も何人かおられました。
皮膚科の基本は皮膚の状態を詳しく観察することです。
そこから得られる情報は無限ですが、多くの皮膚科医は病気だけしか見てません。
日々の食事から作られる皮膚は栄養のあらわれで、賢い鋭敏な皮膚はその異常(栄養障害)を皮膚の変化として知らせてくれます。栄養障害は内臓疾患にもつながるため、皮膚から内臓疾患が見つかるケースもあります。
皮膚疾患の適切な診断も必要でしょうが、皮膚の変化がなぜ生じているかを皮膚科医は理解すべきです。
学会発表をしてきました。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
今回はフェリチンに関する内容でした。
発表後の感想としては、フェリチンも含めて鉄と皮膚に関しては皮膚科はまだまだ理解されていないことと、医師は病気の診断や薬物治療ばかりで栄養についてほとんど関心がないということを実感しました。
学会はお若い医師は原稿を読むだけの練習、年配の医師はお仲間同士のおめでたい集まりであると今回参加して感じました。それにしても医者ってはなぜこんなに話が長いのか聞いていてイライラしました。
一応医学の発展という名目の学会ですが、今回はもう500回以上開催されていますが、毎回同じような内容の発表ばかり、医療費も病気もどんどん増えており、いつも申し上げているように学会の在り方を見直す必要があるかもしれません。
体の仕組みを理解した皮膚科診療
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養療法で学んだことの一つは体の仕組みでした。
これは生化学や生理学であり、医学部では1〜2年の時に講義で受けました。
しかし真面目に授業を聞いておらず、試験だけの一夜漬け暗記でしたので全く理解していませんでした。
医者になって臨床を学ぶようになると、診断法や治療法ばかりを追求して、肝心の病気の原因に関しては、多くの医師がそうであるように難しいことは研究者任せという状態でした。
栄養療法に出会って、病気と栄養の関わりを学んでいくと、
「もっと体の仕組みや病気と栄養の関係を知りたい」と思うようになりました。
私自身、皮膚の変化というのは全ては内臓の異常だと思っています。
皮膚トラブルも体全体を把握した対応をしたいと思っていますが、皮膚科医のほとんどはこうしたことに興味を示されないと思います。
糖尿病合併症と栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
糖尿病合併症には腎症(透析)、網膜症、足の潰瘍や壊死などが知られています。
こうした合併症を起こさないためには血糖コントロールですが、実際は治療をしていても合併症も生じる方も少なくありません。
以前、糖尿病で酒もタバコもされない真面目な方が透析導入や突然死になった例もありました。
こんなことを言いますと糖尿病専門医に怒られるかもしれませんが、
治療を行なっても合併症が生じれば、医師の敗北であると思っています。
しかし実際は、「合併症は仕方がない」として多くの患者さんは受け入れているようです。
さらに、皮膚のかゆみや湿疹、骨折、がんなども糖尿病合併症ですがほとんど理解されていません。普段診療をしていますと、糖尿病の治療をされていても、皮膚トラブルがなかなかよくならない患者さんは大勢おられます。栄養療法を学ぶようになって糖尿病は食事療法や血糖コントロールだけでは不十分であるといつも感じています。
モイゼルト講演会
こんにちは、院長の栗木安弘です。
土曜日はモイゼルト軟膏の勉強会でした。
たまに難しい研究内容を拝聴すると頭は混乱しますが、とても勉強になります。
今回はモイゼルト軟膏の抗菌ペプチド効果やタイトジャンクション修復や抗酸化作用など、モイゼルト軟膏の新たな可能性を感じました。
こうした効果はビタミンDにもあって、アトピーに対してはモイゼルト軟膏外用とビタミンD内服も相乗効果が期待できるかと思いました。
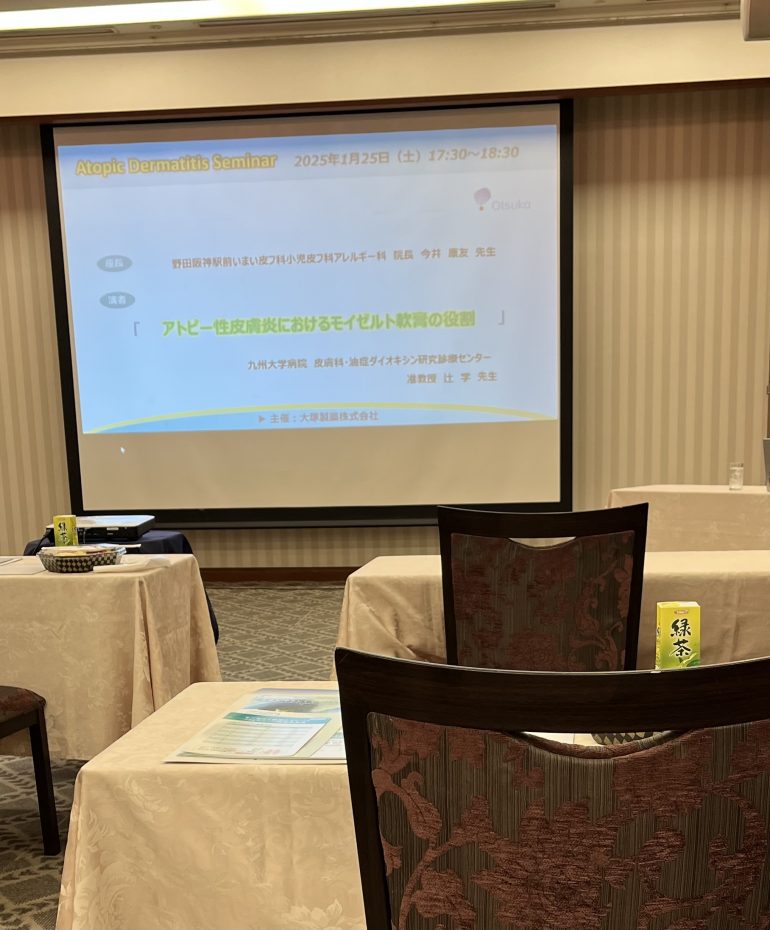
震災の日
こんにちは、院長の栗木安弘です。
今日は阪神淡路大震災から30年目の日です。
当時は医者になったばかりで、皮膚科医ではなく救命センターでの研修期間中でした。
そんな時に災害医療というのものを経験しました。
そういったことを踏まえて、一時は皮膚科を辞めて救命救急への転科も考えていました。
あれから30年、紆余曲折ありましたが、
栄養療法に出会って皮膚科を選択してよかったなぁと思っています。